求人市場が大きく変わりました。
かつての有名求人サイトの多くがサービスを変更し、今や「Indeed」が圧倒的な力を持っています。
ハローワークも苦戦しており、企業は新たな採用手法を模索する時代です。
この記事では、なぜIndeed一強になったのかを解説します。
そして、これからの採用で重要になるSNS活用法まで、分かりやすくお伝えします。
第一章 懐かしのあの頃?数年前までの求人メディア勢力図
数年前まで、日本の求人市場は全く違う景色でした。
多くの企業が、当たり前のように有名な求人サイトを利用していました。
「リクナビNEXT」や「マイナビ転職」が、中途採用の二大巨頭として君臨していました。
新卒採用と同じように、この2つのサイトに掲載すれば安心、と考える企業が多かったのです。
アルバイトやパートの採用では、「タウンワーク」が絶大な力を持っていました。
駅やコンビニに置かれた無料のフリーペーパーは、多くの人の仕事探しの入り口でした。
ウェブサイトと紙媒体の両方で、地域に密着した情報を提供していました。
企業側は、これらのメディアに求人を掲載するために、決して安くはない料金を支払っていました。
掲載期間や原稿のサイズによって料金が異なります。
数十万円から百万円を超えることも珍しくありませんでした。
それでも、人を採用するためには必要な投資だと考えられていたのです。
第二章 激変!2025年、求人メディアに何が起こったのか
2025年に入り、その常識は完全に覆されました。
長年続いた求人メディアの勢力図が、一瞬で塗り替えられたのです。
まず、リクルートが運営する「リクナビNEXT」や「タウンワーク」のサービスが大きく変わりました。
2025年3月末で、従来の掲載課金プランがすべて終了したのです。
同時に、「タウンワーク」のフリーペーパー全77誌も休刊となりました。
これらのサービスは、「Indeed PLUS」という新しい仕組みに統合されました。
これは、Indeedのシステムを通じて、リクナビNEXTやタウンワークのサイトにも求人が掲載されるというものです。
つまり、実質的にIndeedの支配下に入った、と見ることもできます。

一方で、求職者にとって最後の砦とも言える「ハローワーク」も、その役割を十分に果たせなくなっています。
人材採用に関する情報メディア「求人サイト制作ナレッジルーム」は2025年5月20日、この状況を次のように報じています。
「ハローワーク、採用率が過去最低の11.6%に──9割が空振り、ミスマッチ拡大で役割に再考迫られる」
この記事が示す通り、ハローワークに出された求人の約9割が採用に結びついていないのが現状です。
なぜなら、求職者が求める働き方と求人内容のミスマッチが深刻化し、民間の求人サービスに比べてシステムの利便性も劣っているためです。
無料で利用できるというメリットはありますが、もはや採用の主軸とするには厳しい状況と言わざるを得ません。
第三章 なぜ?Indeed一強時代が訪れた理由を考察
では、なぜこれほどまでにIndeedだけが強くなったのでしょうか。
その理由は、Indeedのビジネスモデルそのものにあります。
Indeedは、一言で言えば「求人情報に特化した検索エンジン」です。
Googleが世界中のウェブサイトを検索できるように、Indeedは世界中の求人情報を検索できます。
自社サイトだけでなく、他の求人サイトや企業の採用ページまで自動で情報を集めてくるのです。
この「網羅性」が、仕事を探す人にとって非常に便利でした。
従来の求人サイトは、自社に掲載料を払ってくれた企業の求人しか載せていませんでした。
そのため、求職者は複数のサイトを行き来して、情報を探す必要がありました。
しかしIndeedなら、一か所でまとめて探せるのです。
この圧倒的な利便性に、多くのユーザーが惹きつけられました。
ユーザーが集まれば、企業もそこに求人を載せざるを得ません。
こうして、Indeedはどんどん力をつけていきました。
他の求人メディアは、ユーザーの行動変化とIndeedの利便性の前に、なすすべもなく没落していったのです。
掲載課金という古いビジネスモデルが、時代の流れについていけなかった結果とも言えるでしょう。
第四章 Indeedだけじゃない!これからの採用、どうする?
Indeedが非常に強力なツールであることは間違いありません。
しかし、一つのサービスに採用活動のすべてを依存してしまうのは、リスクも伴います。
広告費が高騰する可能性もありますし、Indeedのルール変更一つで採用がストップする危険性もあります。
これからの時代に求められるのは、「攻めの採用」です。
求人サイトで応募を待つだけでなく、企業側から積極的に候補者を探しにいく姿勢が重要になります。
そのための最も強力な武器が、TikTokやInstagramリールといったショート動画系のSNSです。
なぜなら、今の若者層は長い文章を読むことを好まず、短い動画でテンポよく情報を集めるのが当たり前になっているからです。
これらのプラットフォームでは、企業の日常や文化、働く人々のリアルな姿を動画で発信することができます。
テキストだけの求人情報では伝わらない、会社の「生きた魅力」を直感的に伝えることができるのです。
すぐに転職を考えていない「転職潜在層」にも、自社の存在をアピールできるのが大きなメリットです。
日々の発信を通じてファンを増やし、「この会社で働いてみたい」と思ってもらう。
そうすれば、いざ求人を募集した時に、質の高い応募が集まる可能性が高まります。
Indeedと並行して、今からでもSNSアカウントを育てていくことが、未来の採用成功への鍵となるでしょう。

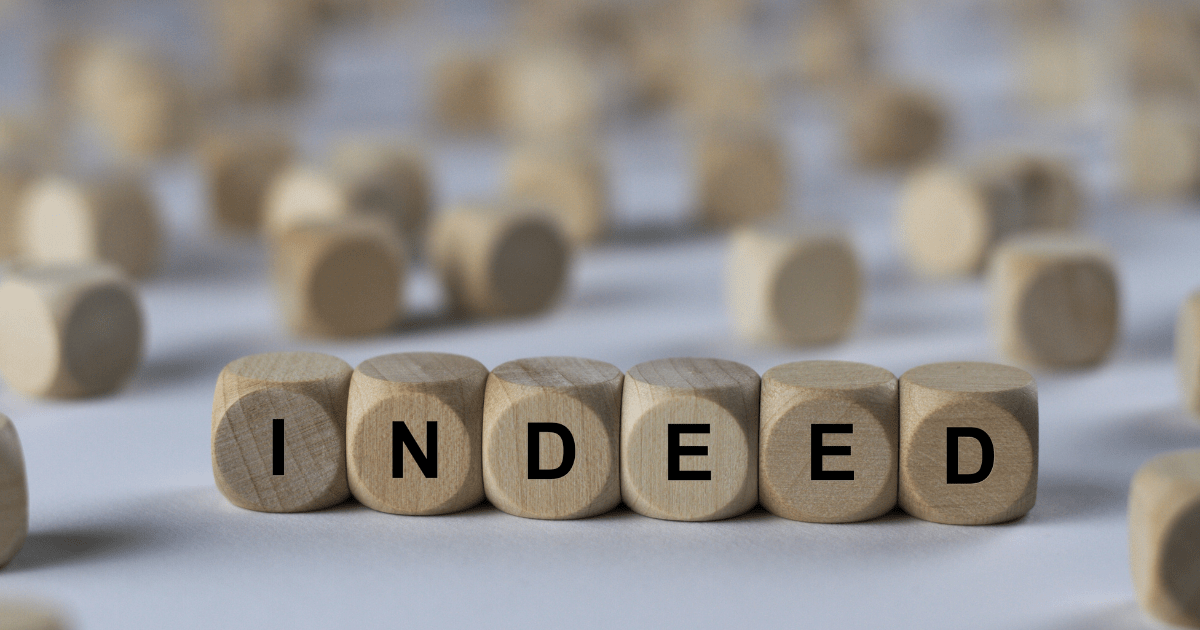



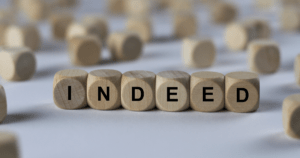

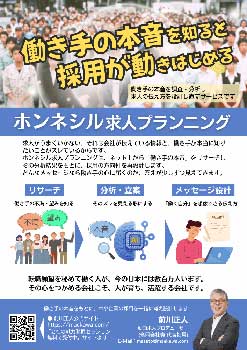

コメント