製造業の採用活動では、従来の工場見学は効果的です。
でも、それを頻繁に実施するのは困難です。
そこで動画による「オンライン工場見学」はどうでしょう?。
この記事では、採用施策としての工場見学動画の活用法について解説します。
第1章 職場を事前に知ることは重要
製造業で働く前に、職場の雰囲気や環境を知ることは極めて重要です。
未経験の求職者にとって工場内の様子は未知の世界です。
どんな人たちがどんな環境で働いているのでしょうか。
これらの情報は企業への興味や親しみを大きく左右します。
そのため一部の製造業では、採用応募者を対象とした工場見学ツアーを実施しています。
製造業では求人に応募した転職希望者や新卒者を対象に、工場見学を実施することがあります。
工場見学を実施する1番の目的は、採用のミスマッチを防ぐことです。
実際に工場見学を経験した人の多くが好意的な感想を持っています。
見学をした人の場合、ほとんどの人が「見学してよかった」という感想を抱いています。
職場の雰囲気や実際の作業風景を直接確認できることで、求職者は安心して応募できるのです。
第2章 工場見学ツアーの課題と動画による解決策
工場見学ツアーは確かに効果的です。
しかしそれを頻繁に実施するのは業務上困難です。
生産ラインを止めるわけにはいきません。
見学者の安全確保も必要です。
コストと時間もかかります。
そこで提案したいのが、動画による工場見学です。
一度撮影すれば何度でも活用できます。
時間や場所の制約もありません。
求職者は好きなタイミングで、自分のスマホから視聴できます。
採用施策として工場見学動画を作るのなら、ただ設備を映すだけでは不十分です。
重要なのは、そこで働く従業員たちの姿を見せることです。
実際に作業している人たちの表情や動き。
チームワークの様子。 休憩時間の雰囲気。
これらの映像は求職者にとって「将来の自分」をイメージさせる貴重な材料となります。
職場の人間関係や働きやすさが伝わる映像こそ、採用において最も価値があるのです。

第3章 バーチャルツアー形式で自由な見学体験を
工場見学動画のいち変形版といえるのが、バーチャルツアー形式の工場見学動画です。
この仕組みは、Webサイトに工場の内部配置図を掲載することから始まります。
配置図には各エリアや設備の位置が分かりやすく表示されています。
そして図の各部分をクリックすると、その部分を撮影した短い動画が再生される仕掛けです。
例えば「原料投入エリア」をクリックすれば、そこでの作業風景の動画が始まります。
「品質検査室」をクリックすれば、検査の様子を見ることができます。
「従業員休憩室」をクリックすれば、職場の雰囲気を感じられるでしょう。
このバーチャルツアー形式には大きなメリットがあります。
動画ひとつひとつの長さは短いので、視聴者が飽きることがありません。
自分で好きな部分を選んで見て回ることができます。
興味のある工程だけを重点的に確認することも可能です。
求職者の立場で考えてみましょう。
「自分が配属される可能性の高い部署はどこだろう」
「どんな設備を使って作業するのだろう」
こうした具体的な関心に合わせて、ピンポイントで情報を得られるのです。
一方でデメリットもあります。
全部を見ないまま離脱されてしまう場合があることです。
しかしこれは興味がない部分をスキップしているだけなので、実害は少ないと考えられます。
むしろ無理に全部見せようとして離脱されるより、興味のある部分だけでも深く見てもらう方が効果的でしょう。
バーチャルツアー形式は、求職者主導の能動的な情報収集を促します。
自分で選択して視聴した情報は、記憶にも残りやすいのです。
第4章 マイクロドローンが切り開く新たな映像表現

マイクロドローン(イメージ)
別のアプローチとして、マイクロドローンを活用した工場見学動画を提案しましょう。
従来のドローンといえば屋外での空撮を想像します。
しかし近年、手の平に乗るほど小型で超軽量な「マイクロドローン」が使われるケースが増えています。
小回りが利くため、障害物の多いオフィス内や工場内などでの撮影が得意です。
マイクロドローンの最大の特徴は室内での安全な飛行です。
マイクロドローンは他のドローンに比べて非常に小さくて軽量であるため、万が一物や人と衝突してしまっても大事故に繋がらないのです。
このマイクロドローンを使えば、工場内部を自由自在に飛び回ることができます。
作業者の頭上を通り抜ける視点。 製造ラインを縫うような軌道。 機械の隙間から覗く角度。
これまで誰も見たことのない斬新な映像が撮影可能です。
現地へ下見しなくても、その空間の魅力が、リアルにオンライン体験できるマイクロドローンでの動画撮影が実現します。
視聴者は まるで自分が工場内を飛び回っているような臨場感を味わえます。
普通のカメラでは絶対に撮れない、一味違った工場見学動画の完成です。
第5章 撮影の副次効果:5S活動の促進
工場見学動画には意外な副次効果があります。
それは撮影をきっかけとした職場環境の改善です。
動画撮影をすると、見せたくない部分まで映ってしまいます。
整理整頓が行き届いていない工場の隅。
雑然と積み重ねられた資材や工具。 清掃が不十分なエリア。
しかしこれは逆にチャンスでもあります。
撮影を機に全社的な5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を推進できるのです。
「動画に映るから綺麗にしよう」
この意識が工場全体に広がります。
結果として職場環境が格段に向上します。
きれいに整備された工場は、動画映えするだけでなく、実際に働く従業員の士気向上にもつながります。
安全性も高まります。
一石二鳥どころか三鳥の効果が期待できます。
まとめ 内部の真の姿を発信する意義
製造業の工場内で行われていることは、外部の人にはなかなか見えません。
どんな技術が使われているのでしょうか。
どんな人たちが働いているのでしょうか。
どんな雰囲気の職場なのでしょうか。
工場見学動画は、こうした内部の真の姿を外に発信する強力なツールです。
大切なのは、飾り立てることではありません。
ありのままの職場の魅力を伝えることです。
そうすることで、本当にその会社で働きたいと思う人材を惹きつけることができます。
結果として、採用のミスマッチが減り、定着率の向上につながります。
採用コストの削減効果も期待できるでしょう。
製造業の経営者や採用担当者の皆さん。
オンライン工場見学動画の制作を、ぜひ検討していただきたいと思います。









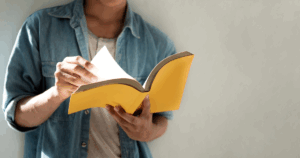

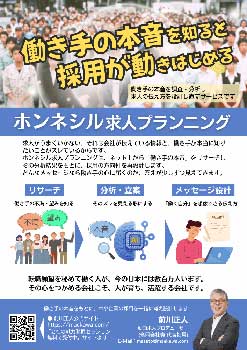

コメント