求人票に「明るく元気な方」と書いていませんか。
それは企業が言いたいことであって、応募者が知りたいことではありません。
映画監督が採用動画制作で気づいた重要な教訓から、応募者数より定着率を高める発信の本質を学びます。
第1章 映画監督が気づいた採用動画の致命的な問題
東洋経済オンラインに興味深い記事が掲載されました。
「エンタメのプロが納得の分析… 「女性向けアダルト配信動画」がもっとも視聴されるのは何曜日?」
筆者は映画監督の李闘士男氏です。
李氏が経営者の友人から採用動画制作の相談を受けたときのことです。
企業側が求める人材を聞いてみると「明るく快活」「やる気がある」「時間を守る」などさまざまな条件が出てきました。
それを聞いた李氏は思わず「それって、本当に就職希望者が知りたいことなの?」と聞き返したそうです。
記事では次のように指摘されています。
「どんな人材を求めているか?」は、採用系コンテンツによくある内容。企業側が求める人物像を伝えれば、それに反応した応募者が来てくれるから、採用後のミスマッチが避けられるという利点はあると思います。
でも、それは、企業側が伝えたい情報であって、残念ながら就職希望者が本当に知りたい情報ではなさそうです。
そこで李氏は「離職の理由(ミスマッチ)を解決」をテーマに動画を作ることを提案しました。
なぜ人が辞めたのか、その理由を明らかにし、実際の現場を見せることで職場の人間関係や雰囲気をつかんでもらおうと考えたのです。
結果はどうだったか。
応募者数そのものは微増でした。
しかし、その動画を見て入社した新入社員たちは入社後もすっと職場の雰囲気になじみ働き続けているそうです。
ミスマッチの防止につながったと喜ばれたそうです。
離職率も低く抑えられています。
第2章 「自分が言いたいこと」より「相手が知りたいこと」
李氏はこの経験から重要な教訓を導き出しています。
大切なのは、「自分が言いたいこと」より「相手が知りたいこと」です。
これは採用に限った話ではありません。
記事では電動歯ブラシを例に挙げています。
1分間に何回振動するか、充電池がどのくらいもつか。
そうした性能自慢も大事でしょう。
しかしお客さんが財布を開く瞬間は、振動数を知ったときではありません。
黄ばんでいた歯が真っ白になる様子を見たときです。
使用者が「ツルツルになってスッキリ!」と爽快感を笑顔で語ったときです。
つまり、受け手がどんなメリットを体験できるのか、が決め手となるのです。
性能というスペックではなく、その先にある体験価値こそが相手の知りたいことなのです。
採用においても同じです。
企業が求める人物像はスペックです。
就職希望者が本当に知りたいのは
「どんな人が働いているのか」
「実際に働いたときの職場の雰囲気」
という体験価値なのです。
第3章 あなたの求人票は誰のために書かれているか
ここで一度立ち止まって考えてみましょう。
あなたの会社の採用ページや求人票は、誰のために書かれていますか。
「明るく元気な方」
「コミュニケーション能力のある方」
「前向きに取り組める方」
こうした文言が並んでいませんか。
それは企業側が言いたいことです。
応募者が知りたいことではありません。
李氏の指摘を思い出してください。
何かメッセージを伝えるとき、「伝えたいこと」ばかりを羅列しても、相手の心を動かせません。それどころか心に届きもしないのです。
どの会社も同じような内容になってしまっては、就職希望者も飽き飽きします。
どの会社も同じに見えていては選べません。
今一度、自分たちが発信している内容を見直してみませんか。
それは本当に相手が知りたいことでしょうか。
具体的にはこう問いかけてみてください。
「応募者はこの情報から何を感じ取れるだろうか」
「入社後の自分の姿をイメージできるだろうか」
「職場の雰囲気や人間関係が伝わっているだろうか」
給料や休日はテキストで伝えられます。
動画や写真だからこそ伝えられる非言語の情報があるはずです。
カメラに向けたよそ行きの姿ではなく、リアルな日常を見せることが大切です。
第4章 ミスマッチを防ぐことで得られる本当の効果
相手が知りたいことを発信することで、どんな効果が期待できるのでしょうか。
李氏の事例では応募者数は微増にとどまりました。
しかし、より重要な成果が得られています。
それは入社後のミスマッチの解消です。
職場の雰囲気を知ったうえで入ってきた新入社員たちは、すぐになじみ働き続けています。
離職率も低く抑えられました。
モチベーションの高い新人が集まったと経営者も喜んでいます。
これこそが中小企業にとって最も価値ある成果ではないでしょうか。
応募者を数多く集めることより、自社に合う人材に来てもらうことのほうが重要です。
入社後すぐに辞められてしまっては、採用にかけた時間もコストも無駄になります。
何より、現場で教える社員の負担が大きくなります。
相手が知りたいことを発信すれば、自然と自社に合う人が応募してきます。
ミスマッチが減れば、定着率が上がります。
定着率が上がれば、組織が安定します。
組織が安定すれば、生産性が上がります。
採用は数の勝負ではありません。
質の勝負です。
そして質を高めるカギは「自分が言いたいこと」ではなく「相手が知りたいこと」を発信することにあるのです。
今日からできることがあります。求人票の文言を一つ変えてみることです。
「こういう人が欲しい」ではなく「こういう職場です」と伝えてみることです。
小さな一歩が、採用の質を大きく変えるはずです。









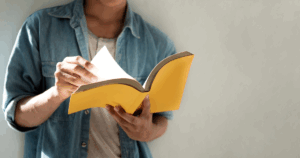

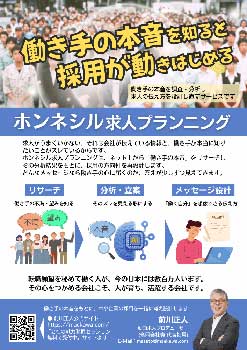

コメント