製造業の勉強会で気づいた衝撃の事実。
人材採用を「経営課題」と語る登壇者がいる一方で、会場には経営者本人の姿はほとんどなし。
日本企業では人材採用が人事担当者任せになっていませんか。
本当の人材採用とは、単なる労働力補充ではなく、会社の未来を左右する重要な経営判断なのです。
第1章 勉強会で見た現実
先日、とある製造業の業界団体が主催する人材採用についての勉強会に参加しました。
十数名の参加者がいたので全員と名刺交換をしました。
ところが、その中に代表取締役の肩書を持つ人がほとんどいませんでした。
多くは総務畑の人事担当者で、位の上の人でも取締役どまりでした。
登壇者は人材採用コンサルタント会社の方と、大手IT会社の人事担当者の方でした。
その中で印象的だったのは、大手IT会社の人事担当者の方の言葉です。
「人材採用は経営者にしかできない重要な経営判断です」とはっきりおっしゃったのです。
会場を見回すと、参加者の多くがメモを取っていました。
しかし、その内容を経営者に伝えて意識変革を促せる人はどれだけいるでしょうか。
「勉強しておけ」と命令されて来た人たちなのではないでしょうか?
日本の経営者たちは人材採用を人事担当者に丸投げするほど、人材採用についての意識が低いのでしょうか。
第2章 人材採用は経営戦略の核心

Image by Umkreisel-App from Pixabay
人材採用はたんなる労働力の補充ではありません。
将来に向けて会社をどのように成長させていくかという経営課題の中の大きな要素なのです。
多くの経営者が見落としているのは、この視点です。
たんに条件に合う人を入社させればいいのではありません。
会社の向かう方向に合わせてどのような人材を獲得していけばいいのか、
ということは経営者自身が真剣に考えなくてはいけない問題です。
人事担当者では判断できない重要な経営判断なのです。
現在の業務をこなせる人材を採用するだけでは、会社の成長は望めません。
5年後、10年後の事業展開を見据えた人材戦略が必要です。
これは経営計画と密接に関わる問題です。
例えば、新しい技術分野への進出を考えているなら、その分野の専門知識を持った人材が必要です。
海外展開を視野に入れているなら、語学力のある人材や国際経験豊富な人材を採用すべきでしょう。
デジタル化を進めたいなら、IT関連のスキルを持った人材が不可欠です。
どの部門を強化するのか。
どんなスキルを持った人材が必要なのか。
社内でどう育成していくのか。
これらの判断は、経営者にしかできない重要な意思決定なのです。
人事担当者に「いい人がいたら採用して」と丸投げしていては、会社の成長戦略は実現できません。
第3章 補助金制度に見る矛盾
もう締め切られましたが「大阪府新事業展開テイクオフ補助金」というものがありました。
この補助金は「人材採用のための費用を補助する」という意味で画期的なものだったと思います。
人材採用に公的な支援があることは、中小企業にとって非常にありがたいことです。
しかし、特に既存事業に対する人材採用のための取り組みに対する補助には矛盾のある規定が設けてありました。
つまり既存事業に対する補助が「生産性の向上を目的とする」が前提とされていたことに問題があります。
この考え方の根本に問題があるのです。
その生産性に特定の公式が当てはめられ下記のように定義されていたことが問題です。
※本事業における「生産性」は以下のように定義します。
「付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)÷従業員数」
つまり「営業利益÷従業員数」の数値を向上させることが補助の条件でした。
これと人材採用の取り組みへの補助はまったく矛盾します。
なぜなら人材採用すれば従業員数は増えるからです。
公式に当てはめれば生産性は下がることになります。
まさに本末転倒と言えるでしょう。
事務局に問い合わせをしたところ、回答は「人材採用のための取り組みをするとともに、利益向上の取り組みをする」ことが条件だということでした。
人を採用しながら、同時に従業員一人当たりの利益を向上させるという条件です。
まったくもって無理ゲーです。
この補助金制度は、人材採用の本質を理解していない典型例だと思います。
そもそも、人材の問題をただ生産性の問題に帰していいものでしょうか。
行政も人材採用を単なる効率化の手段としか捉えていないのかもしれません。
第4章 人材採用の本当の価値
いくら機械やAIを入れて生産性を向上しても、それだけでは会社の未来は保証されません。
有能な人材を獲得することは、将来会社を成長させていく仲間を募ることなのです。
これは投資であり、コストではありません。
単純な生産性の公式に当てはめることはできません。
優秀な人材が入社することで、新しいアイデアが生まれます。
既存の業務プロセスが改善されるかもしれません。
新しい事業分野への進出が可能になるかもしれません。
顧客との関係が深化するかもしれません。
社内の雰囲気が活性化されるかもしれません。
これらの価値は、数字だけでは測れないものです。
長期的に大きなリターンをもたらすのが人材投資の特徴です。
経営者はこの視点を持つ必要があります。
では、経営者は具体的にどのように人材採用に関わるべきでしょうか。
まず、自社のビジョンと戦略を明確にすることです。
どんな会社にしたいのか、明確なイメージを持つことが第一歩です。
次に、そのビジョンを実現するために必要な人材像を具体的に描くことです。
スキルや経験だけでなく、価値観や考え方も重要な要素です。
自社の文化に合う人材かどうかも判断基準になります。
採用活動においても、経営者自らが関わることが重要です。
会社の将来について語れるのは経営者だけだからです。
入社後の育成計画も経営者が関与すべき領域です。
どのようなキャリアパスを用意するのか。
どんな研修や経験を積ませるのか。
これらは人事部門だけでは決められません。
経営者は、会社の未来をどうしていくか考えると思います。
そのときに、それにはどのような人材が必要か考え、行動していくことが求められるのではないでしょうか。
人材採用を人事部門だけに任せるのではなく、経営者自らが関わる必要があります。
どんな会社にしたいのか。
どんな事業を展開したいのか。
そのビジョンを実現するために必要な人材は何か。
これらの問いに答えられるのは経営者だけです。
人材採用は、まさに経営そのものなのです。
人手不足の時代だからこそ、この視点が重要になってきます。

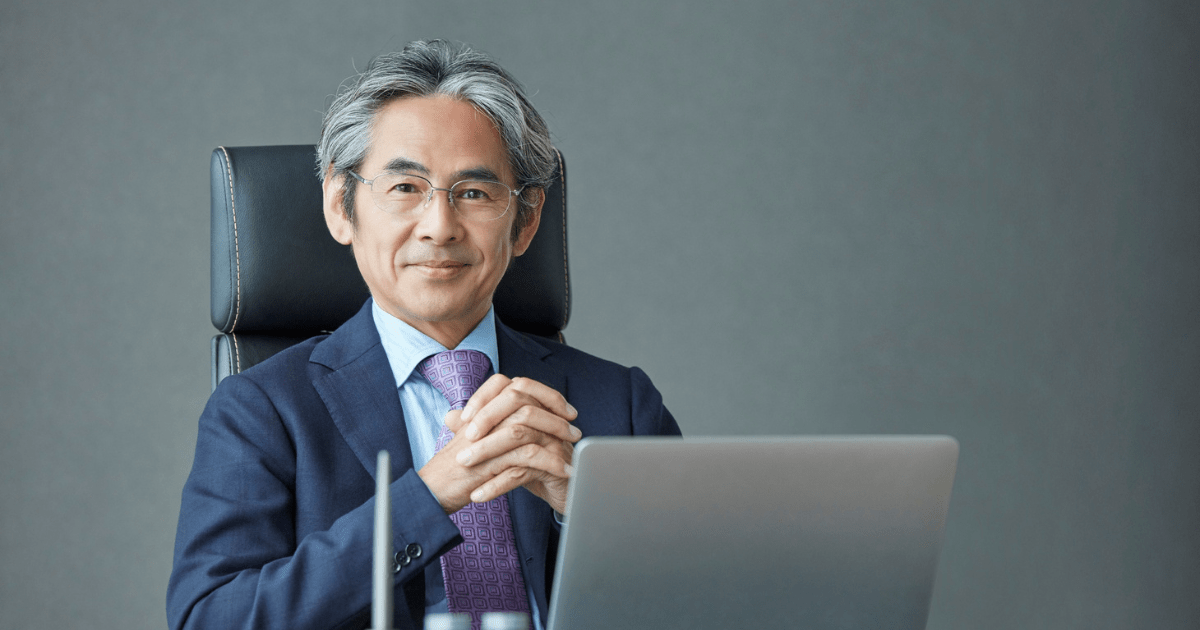





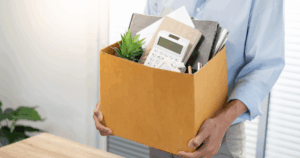



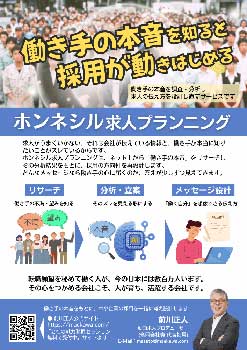

コメント