人手不足に悩む中小企業の経営者の皆さん。
「高給与」や「キャリアアップ」といった従来型の採用メッセージに限界を感じていませんか。
今こそ、逆転の発想でユニークな採用メッセージを発してみてはどうでしょう。
それは「当社はペースを落とします」という宣言です。
一見、時代に逆行しているように見えるかもしれません。
しかし、データが示す事実は、この宣言こそが採用力を高め、生産性を向上させる鍵になる可能性を示しています。
第1章 高市発言が映し出す「昭和の労働観」
2025年10月4日、自民党の総裁に就任したばかりの高市早苗氏が「私はワークライフバランスという言葉を捨てます」と発言しました。
ニュースでも大きく取り上げられましたから、ご存知の方も多いでしょう。
「働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」と続け、自民党の国会議員に向かって「馬車馬のように働いていただきます」とも述べました。
この発言は大きな反響を呼びました。
過労死弁護団全国連絡会議は10月6日に声明を発表し、発言の撤回を求めました。
この発言の背景には、昭和時代の労働観があると考えられます。
1973年のフルタイム労働者の所定労働時間は週48時間でした。
週43〜48時間の層が最も高い割合を占めていました。
長時間労働が当たり前だった時代です。
「働けば働くほど成果が出る」という信念がありました。
しかし、この労働観は本当に正しかったのでしょうか。
第2章 長時間労働は本当に生産性を高めるのか
日本生産性本部が2024年に発表したデータを見てみましょう。
2023年の日本の時間当たり労働生産性は56.8ドルでした。
OECD加盟38カ国中29位です。
就業者一人当たり労働生産性は92,663ドルで、OECD38カ国中32位でした。
G7諸国の中では最低です。
一方、厚生労働省のデータによれば、年間総実労働時間は減少傾向にあります。
一般労働者の労働時間は2000時間台で推移しており、最近はさらに減少しています。
つまり、労働時間は減少したのに、生産性は依然として低いままなのです。
この事実が示すことは明白です。
長時間労働と生産性の間には、明確な相関関係がありません。
むしろ、労働時間を減らしても生産性が上がらない日本の労働環境に、構造的な問題があると言えます。
「働けば働くほど成果が出る」という昭和の労働観は、データによって否定されているのです。
第3章 企業調査が示す「ペースを落とす」効果
では、ペースを落とすとどうなるのでしょうか。
Forbes Japanの記事『生産性レースに勝つのは「ウサギではなくカメ」 今あえて仕事のペースを緩めるべき理由』(https://forbesjapan.com/articles/detail/83411)で紹介された企業343社の調査結果は、驚くべきものでした。
優位に立とうと性急に取り組みを進めた企業がありました。
一方で、重要な場面で一旦止まって方向性の正しさを確認した企業もありました。
結果は明確でした。
後者の企業の方が、売上高と営業利益が高かったのです。
「スピードアップのためにペースを落とした」企業のデータは圧巻です。
3年間で売上高が平均40%増加しました。
営業利益は52%も増えました。
収益を大きく押し上げたのです。
なぜペースを落とすと業績が上がるのでしょうか。
調査によれば、こうした企業にはいくつかの特徴がありました。
アイデアや議論に対してオープンになりました。
革新的な思考を奨励しました。
振り返りや学びのための時間を確保しました。
組織の目的・価値観・行動の一体化(アライメント)を優先しました。
対照的に、常に速く動き、効率を最大化することに集中した企業はどうだったでしょうか。
試行された方法に固執しました。
従業員のコラボレーションを促進しませんでした。
アライメントにさほどこだわりませんでした。
結果、業績が悪化したのです。
第4章 採用力を高める逆転の発想──「当社はペースを落とします」という宣言
ここで冒頭の問いに戻りましょう。
「当社はペースを落とします」という宣言は、採用力を高めるのでしょうか。
答えはイエスです。
若い世代の価値観を見れば、その理由は明白です。
SHIBUYA109 lab.が2024年に実施した調査によれば、Z世代の87.9%が「ワークライフバランスを大事にしたい」と回答しました。
男性で82.5%、女性で91.4%です。
企業選びで最も注目するのは「福利厚生の内容」で55.3%でした。
リクルート就職みらい研究所の2024年卒調査でも同様の傾向が見られます。
「仕事と私生活のバランスを自分でコントロールできる」を支持した学生は88.5%でした。
2014年卒の82.6%から5.9ポイント増加しています。
さらに決定的なデータがあります。
ONE CAREERが2026年卒を対象に実施した調査です。
志望企業を決める軸の第1位は「ワークライフバランスの確保」で16.0%でした。
「なりたい職種」「自分の成長」「給料」を抜いて最多だったのです。
株式会社Reviveが2024年に実施した若手世代のワークライフバランス意識調査も見逃せません。
企業に期待する取り組みの上位3位は次の通りでした。
労働時間の適正化、有給休暇の取得推進、柔軟な勤務体制です。
これらのデータが示すことは何でしょうか。
若い世代は、ワークライフバランスを最優先事項として企業を選んでいるのです。
中小企業の経営者の皆さん。
大手企業と給与や知名度で競争するのは困難です。
しかし「ペースを落とす」という宣言なら、明日からでもできます。
「当社は無理なスピードを求めません」
「じっくり考え、学び、成長できる環境を提供します」
「ワークライフバランスを犠牲にしない働き方を実現します」
こうしたメッセージは、若い世代の心に響きます。
そして第3章で見たように、ペースを落とすことは生産性を高める可能性があるのです。
人手不足の時代だからこそ、逆転の発想が必要です。
「当社はペースを落とします」という宣言。
それは採用力を高め、同時に生産性を向上させる、一石二鳥の戦略になるかもしれません。
データが示す事実に目を向けてください。
そして、勇気を持って新しい採用メッセージを発信してみてはいかがでしょうか。







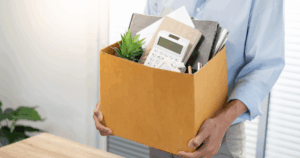



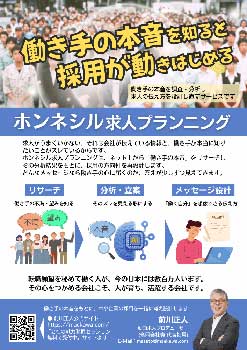

コメント