若い世代の「残業キャンセル界隈」という価値観の変化に、多くの経営者は戸惑いを感じています。
しかし実際に残業ゼロを実現した企業では、売上減どころか増収を達成し、離職率も大幅に改善しました。
懸念される問題と実際の効果を検証します。
第1章 「残業キャンセル界隈」とは何か
「残業キャンセル」という言葉を聞いたことはありますか。
これは定時になったら躊躇なく帰宅する行為を指します。
従来であれば「仕事が残っているのに帰るなんて」と眉をひそめられた行為です。
しかし若い世代にとって、これは当然の権利という認識です。
就業時間が終われば帰る。
極めてシンプルな考え方といえるでしょう。
もう一つ理解しておきたいのが「界隈」という言葉の使われ方です。
従来は地理的な範囲を示す言葉でした。
しかし最近は、特定の価値観や趣味を共有するグループを指すネットスラングとして使われます。
つまり「残業キャンセル界隈」とは、残業を拒否することに共感する人たちのコミュニティを表現した言葉なのです。 単なる個人の行動ではなく、一つの文化的現象として捉える必要があります。
この価値観の変化は数字にも現れています。 かつて就活生が重視していたのは給与と安定性でした。
「少しでも初任給がいいところに勤めたい」
「将来性があって安定している会社がいい」
経済的な豊かさが最重要でした。
しかし今は違います。
「お給料はそこそこでいいから、ハードじゃない職場がいい」
「残業が少なくて、休みも取りやすい会社がいい」
「基本がリモートワークで、満員電車に乗らなくて済む会社がいい」
働き方そのものが重視されるようになったのです。
経営者世代には理解しがたい価値観かもしれません。
しかしこれが現実です。
人材獲得競争において、この変化を無視することはできません。
第2章 残業ゼロで採用競争に勝った実例
東洋経済オンラインの記事
「『仕事を終わらせずに帰るなんて責任感がない』という声もあるが…『残業キャンセル界隈』を肯定する会社が”残業ゼロ”に舵を切った結果」
で紹介されたみらいパートナーズの事例は、この価値観変化への対応として非常に興味深いものです。
同社は物流・BPOサービスを手がける労働集約型企業でした。
もともと残業が月40時間程度に達していました。
社員に長く働いてもらうほど売上が上がるビジネスモデルだったからです。
社員も残業代目当てで進んで残業していました。
しかし2010年代の社会情勢変化を受け、2021年に「残業ゼロ」を宣言しました。
働き方改革を進める企業の多くが「残業月10時間以内」程度の目標を掲げる中、完全なゼロを目指したのです。
結果は劇的でした。 残業ゼロを打ち出した2021年、応募数は前年比165%に増加。
中には信じられずに、わざわざ本社に確認に来る学生もいました。
就活生にとって「残業ゼロ」のインパクトは絶大だったのです。
既存社員への影響も良好でした。
離職率は2020年の20%から2025年の5%へと大幅に改善。
エンゲージメントスコアも向上しています。
残業代がなくなることを理由に退職した社員は1名のみ。
同社は月2万円の大幅ベースアップで手取り減を補償しました。
結果として、残業ゼロにしても売上は減るどころか増加したといいます。
第3章 経営者が抱く残業ゼロへの懸念
多くの経営者が残業ゼロに踏み切れない理由として、以下のような懸念が挙げられます。
売上への影響
労働時間が減れば、処理できる仕事量も減る。
特に労働集約型ビジネスでは、この影響は深刻に見える。
人件費の問題
残業代がなくなれば社員の手取りが減る。
それを補うベースアップには原資が必要。
売上減と人件費増のダブルパンチで利益が圧迫される。
社員のモチベーション低下
「時間になったら帰っていい」環境では責任感が薄れるのではないか。
仕事への取り組み姿勢が甘くなるのではないか。
顧客への影響
急な案件や緊急対応時に残業ができなければ顧客満足度が下がる。
競合他社に負けてしまう可能性もある。
業界全体の慣習
取引先や競合が長時間労働前提の中、自社だけ残業ゼロは勇気が要る。
「甘い会社」と見られるリスクがある。
これらの懸念は理解できます。 しかし実際のところ、どうなのでしょうか。
第4章 残業ゼロが生み出す意外な生産性向上
残業ゼロの実現は、実は多くの企業にとってプラスの効果をもたらします。
その理由を理論的に考えてみましょう。
まず時間制約による集中力の向上です。
残業ができる環境では、どうしても時間に対する意識が甘くなります。
「今日中に終わらなくても残業すればいい」 そんな心理が働くからです。
しかし残業が禁止されれば、限られた時間内で成果を出さなければなりません。
この制約が集中力を高め、無駄な作業を排除する動機となります。
みらいパートナーズの例では、8時間でできる仕事を9〜10時間と見積もっていた無駄が発見されました。
次に業務効率化への取り組みです。 時間制約があることで、現場レベルでの改善意識が高まります。
デジタル化の推進、無駄な会議の削減、業務プロセスの見直し。
これまで後回しにしていた効率化施策に本格的に取り組むようになるのです。
人材の定着率向上も重要な要素です。
働きやすい環境は優秀な人材の流出を防ぎます。
採用コストの削減、ノウハウの蓄積、チームワークの向上。
これらが長期的な生産性向上につながります。
さらに、今の時代において残業ゼロは強力な採用ツールになります。
優秀な人材ほど働き方を重視する傾向があります。
彼らを獲得できれば、短時間でも高い成果を上げることが可能になるでしょう。
重要なのは経営トップのコミットです。
中途半端な取り組みでは効果は期待できません。
しかし本気で残業ゼロに取り組めば、多くの企業で生産性向上と働きやすさの両立が実現できるはずです。
「残業キャンセル界隈」が示す価値観変化。
これは単なる若者のわがままではなく、
より効率的で持続可能な働き方への転換を求める声なのです。







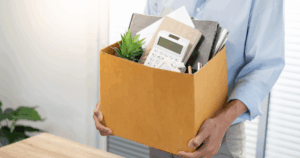



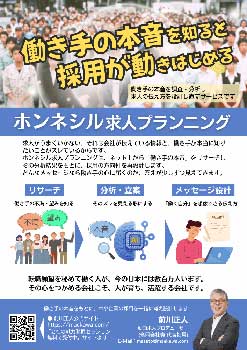

コメント